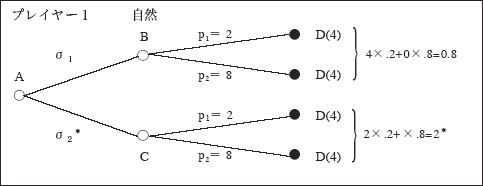1940年11月、T. パーソンズとA. シュッツは、シュッツが英国の雑誌『エコノミカ』に寄稿したパーソンズの『社会的行為の構造』(1937)の書評を巡り、学問的な文通を始めた。双方の理論的背景が類似していたにもかかわらず、そのやりとりは方法論と行為論を巡る激しい議論の末、1941年4月には終わってしまった。本稿では20 世紀初頭の経済学における方法論的問題を考察したうえで、パーソンズとシュッツの行為論に焦点を当てていきたい。
1. シュッツとパーソンズの理論における経済学的背景
シュッツとパーソンズ双方の理論的背景は20世紀初頭の経済理論における方法論的な論争である。ウィーン大学で経済学を学んだシュッツはオーストリア学派経済学の影響を受けた。〔当時〕オーストリアの経済学者は、「方法論争」と呼ばれる、ドイツ歴史学派との激しい論争の直中にいた。この論争は、C. メンガー(1840-1921)と、ドイツ歴史学派のリーダーであるG. シュモラー(1838-1917)との間で1883 年に始まる。メンガーは方法論的個人主義の原則に一致した、純粋理論としての経済学的アプローチを提案した。彼によれば、経済学は人間の行為とそれに先行する状況という一般的な普遍概念に、そして演繹法に基づくべきであった。一方、シュモラーは具体的歴史的事実の記述と帰納法に基づく、経済学的アプローチに同意していた。全体としての経済が彼の研究戦略の対象だったのである[Fusfeld, 1987: 454; Prendergast, 1986: 22]。シュッツはオーストリア学派の方法論的立場を擁護しようとし、M. ヴェーバーに注目した。ヴェーバーは、かの論争において中間的立場にいた。彼は一般的な社会学概念を用いて歴史的社会過程の記述を試みていた[Prendergast, 1986: 1ff]。シュッツはヴェーバーの理念型概念の中に、そして彼の「理解」の方法の中に、自らの方法論上の問題への解決策を見出した。それのみならず、ヴェーバーの「理解」の方法を解明するため、〔さらに〕意識の流れの分析に基づくフッサールの現象学に注目した。こうした考察から結局シュッツは、間主観的理解という問題を扱うため行為論はどのように構成されるべきかという問題に導かれることになる。よって、シュッツの主要な分析〔対象〕は、動機の(主観的及び間主観的)連関と一般的名辞としての生活世界の構造となった。
パーソンズは、シュッツと同様に、相対立する経済学派の影響を受けた。アマースト大学で彼は制度派経済学者のW. ハミルトン(Walton Hale Hamilton)とC. エアス(Clarence Edwin Ayres)のもとで学び、ロンドン・スクール・オヴ・エコノミクスでは全体としての資本主義をドイツ歴史学派と同様の諸制度の具体的な歴史記述に基づいて分析していたE. キャナン(Edwin Cannan)に学んだ。のちにはハーヴァード大学に赴き、F. W. タウシグ(Frank William Taussig)のような新古典派経済学者と出会うことになる。彼らはオーストリア経済学派が意味するところの方法論的個人主義と一般的な普遍概念に基づく純粋理論を発展させようとしていた。〔シュッツと〕同じく、パーソンズもこの方法論的矛盾を解決するためヴェーバーの理論に注目する。ところがシュッツとは対照的に、ヴェーバーのいうプロテスタントの倫理の分析と価値合理性概念に関心を持ち、彼の方法論的研究のほうには関心がなかった。経済学の〔方法〕論争においてパーソンズとシュッツは明らかに異なる側面へ焦点を当てんとしていた。この論争は主に2つの争点に関わる—それは [1] 個別的な行為の影響を大抵は受けない、全体としての社会 対 個別の1行為の結果としての社会というものと、[2] 無二の歴史的事実 対 一般的な普遍概念とそれらの因果関係という争点である。パーソンズはシステムと個別的行為者の葛藤に関心を寄せていた。一方、シュッツは歴史的事実と一般的概念の問題に取り組んだ。結局、パーソンズは生化学者L. J. ヘンダーソン(Lawrence J. Henderson)の立場を採用する。ヘンダーソンはそのV. パレートについての講義でシステムと一般概念の重要性を強調していた。パーソンズは一般概念を自分の主要な方法論的道具として受け入れる。一方では全体としての社会(制度派経済学)もしくはシステム(ヘンダーソン)、他方では個人的行為者(新古典派経済学)という、基本的なズレを統合する試みが自身の研究計画を画定した[Camic, 1991: xxxiif. , xxxv をも参照]。パーソンズにとっての問題は、個人の利害と集団の利害の間の根本的な葛藤を除去する、利己的効用への配慮を基礎に据えた行為論の構築だった。
2. SEU理論・ゲーム理論・パーソンズとシュッツの行為論
シュッツとパーソンズ〔それぞれ〕の異なる行為論をよりよく理解するためには経済学における行為論の記述から始めるのが有益である。〔そうすれば〕シュッツとパーソンズの間の差異はより見えやすくなるだろう。というのは、パーソンズの行為論が主観的期待効用(subjective expected utility: SEU)理論に類似している一方で、シュッツのそれはゲーム理論により密接に関連するからである。
図表1 SEU理論におけるディシジョン・ツリー:自然に対するゲーム
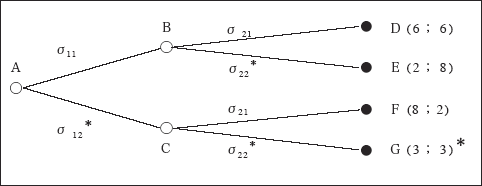
近代経済学では人間行動を記述するため、異なる2概念が使われている。〔第1に、例えば〕セキュリティに関しては、限界効用概念が適用される。この概念は、シュッツとパーソンズの断絶ともいえる差異にとっては重要ではないので、さらに論じるつもりはない。人間行動における第2の、より興味深い説明はリスクに関してであり、それはSEU概念に基づいている(図表1参照)。行為者が決定の状況に直面するとしよう。そこでは、少なくとも2つの択一的な戦略σi から選択しなければならない。彼は期待=予期された環境ej のさまざまな状態について、それぞれの選択肢u(xi) の帰結と効用を見極める。そして彼は、環境ej の〔期待=予期された〕全ての状態について、選択肢σi の全ての期待効用を、状態ej が生起するであろう蓋然性pj を加重し、合計する:U (σi) = Σ pju(xij)。この決定問題の例に、自分の空き時間の調整法を決めることになった行為者を挙げてみよう。彼は森を散歩すること(図表1のσ1)ができる。その場合、陽が照っていれば彼は満足するだろう( u(x11) = 4 )。また、読書(図表1のσ2)ができるが、これなら天気に関係なく彼は満足するだろう( u(x2j) = 2 )。これは選択肢の期待効用と陽が照る蓋然性(p1=20%)に依存する。こうした決定状況は、経済学では自然に対するプレイと呼ばれている。
ゲーム理論は、新古典派ミクロ経済学とは対照的に、(自然に対してゲームを行う)単離した行為者(isolated actors)の行動を分析するのではなく、2人以上の行為者の諸決定の戦略的相互依存性を扱う(図表2参照)。さて、二番手の行為者は一番手の行為者の行為σ1i にリアクションを起こす機会σ2i があり、したがって、一番手の行為者は二番手の行為者のリアクションを考慮に入れつつ決定を下すことになる。この反省の結果、彼は後向き帰納法戦略を使って、ゲームを解いていくだろう。彼はまず二番手が何を選択するつもりなのかを自らに問い、それから、これらの起こりうるリアクションの中から彼にとって最良のリアクションを選択することになろう。図表2においては、EはDよりも良く、GはFよりも良いので、二番手のプレイヤーは、どの場合でもσ22 を選択することになるだろう(2列目の数は二番手の効用を表す)。したがって、一番手は、彼にとって結果Gは結果Eよりも良いものなので、戦略σ12 を選択することになるだろう。こうした決定状況の一例に囲碁がある。そこでは、各プレイヤーは他のプレイヤーの起こしうるリアクションを考慮した上で、ゲームに勝利するための戦略を見出さんとするのである。→続きを読む(頒布案内)
図表2 ゲーム理論におけるディシジョンツリー:他の主観とのゲーム